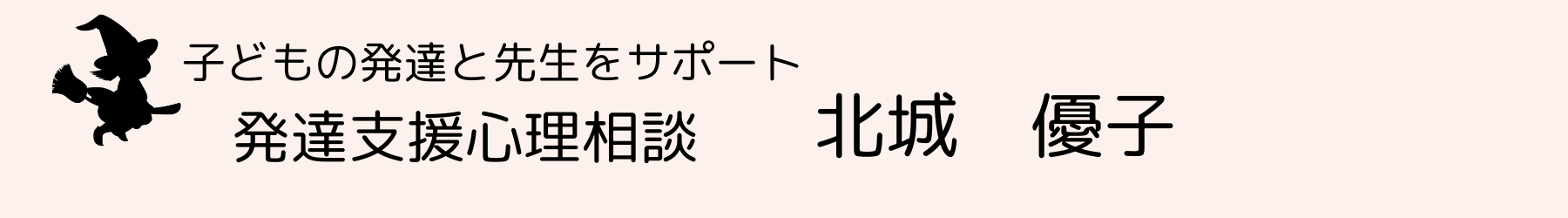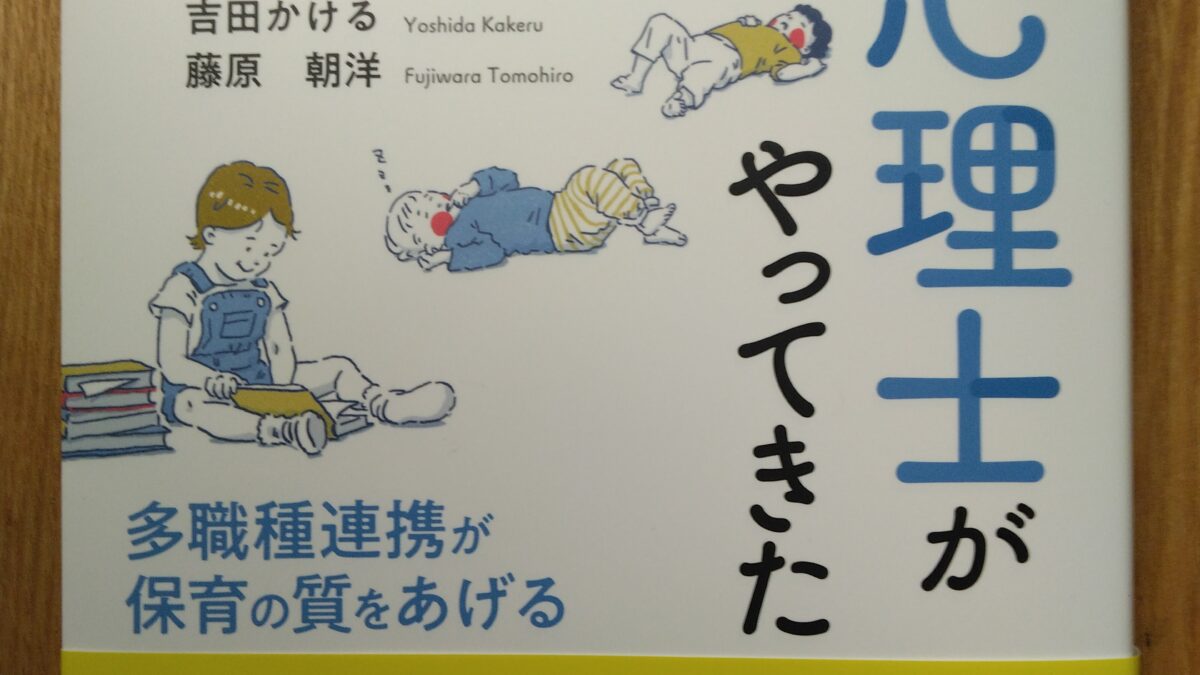◎ついにそのときがやってきた
「保育園にもカウンセラー(心理職)がいてほしい」と
自分の体験をきっかけにそう考えるようになったのが
今から約10年ほど前…
ついに見つけてしまいました!!
この本!!
タイトルをみつけた瞬間、胸がドキドキしました。
「実現したんだ!」(自分じゃないけど)
帯には「画期的な取り組み!」と書いてある。
「てことはまだ前例があんまりないってことかー」
「やっぱり必要なんだよねー」
「同じ思いの人がいて、実現してたんだねー」
「うれしいねー」
「本になったら、これからどんどん広がっていく可能性があるってことだよね」…
いろんな思いがめぐりました。
ホント、うれしい!感動!
話聞きに行こう^^
語り合いたい!
◎保育園に心理士がやってくることになったきっかけ
この本は、
京都の社会福祉法人の認可保育園「みぎわ保育園」が常勤心理士を導入し、
保育士との連携を通じて、要支援児であってもそうでなくても
すべての子どもたちに成長の機会を保障できるような
ユニバーサルデザイン保育を実現していく過程を
若手心理士の試行錯誤と実践を通じて描いた記録です。
支援を必要とする子どもを園で預かれなかった経験や
発達支援のノウハウが園に蓄積されてこなかった状況をきっかけに、
「発達支援の専門家(心理士・言語聴覚士・理学療法士)を直接雇用し、
保育園独自でできる支援の幅を自分たちで拡げよう(本文より)」
と決断されたのだそうです。
「保育園で過ごす日々のなかで専門的なサポートが受けられるような
体制と環境を本気でつくろう(本文より)」となさったのですね。
◎保育園での心理職の役割
読み進めていくと、
みぎわ保育園では心理士が「発達支援」に軸足を大きくおきながら
保育士たち(や他の職種の方たち)と連携し、
子どもたちの成長に関わっていく様子がわかります。
私自身は、ハードワークや仕事での大きなストレスから
体調をくずした経験がきっかけで、
カウンセラー(心理職)が必要と考えるようになりました。
子どもの特性と関わりを深く理解するために
心理士の方に単発で何回か来ていただいたことはありましたが、
おもには保育園の職員たちや保護者に向けて心理職の方にいてもらいたかった。
当時のスクールカウンセラーも
子ども・保護者・教員たちのカウンセリングを行っていたと聞いていました。
「保育園に心理職を」というのが同じ思いであっても
目的や求める仕事内容は違っていたのですね。
心理士の吉田かけるさんは、
最初平日は医療機関で勤務しながら、土曜日だけ保育園で働くという
二足のわらじスタイルで保育園での心理職をスタートされます。
そして、2019年4月から常勤職員として雇用され、
みぎわ保育園初の心理士の常勤職員が誕生となりました。
◎時の流れにともなって変化してきたこと
私自身が療育に関わり始めたのも同じ頃ですので、
やはり、発達支援に関してたくさんの人の意識が高まって
かたちとなってあらわれてきた頃なのかもしれません。
「発達障害」という言葉や認識も広がってきました。
発達支援が必要な子どもたちが療育を受けるための
放課後等デイサービスや児童発達支援の事業所の数も増えました。
本当にいろんな事業所があります。
私は保育園での勤務が長かったので、
支援が必要な子には大人が十分につきながら(加配)
いろんな子たちがいる集団のなかで育ち合うのが望ましいと考えています。
放デイや児童発達支援の事業所では、
いろんな特性があり、支援が必要な子たちばかりがいる場所だからこそ
起こりがちなトラブルや気持ちのつまずきがあると感じるからです。
それに、発達について考えると、
障害があるなしに関係なくその道すじは同じなので、
発達段階に適した関わりのなかで大切にすることも同じです。(発達特性をあわせ考えながら)
その子の発達を深く理解しながら、その子に合った働きかけをするということは
どの子に対しても行うことなので、
みぎわ保育園のめざしておられる「ユニバーサルデザイン保育」の考え方は
私にもとても理解ができましたし、深く共感しました。
◎保育園に心理士がいることのススメ
みぎわ保育園の実践をふまえて、法人顧問の塩谷さんは保育関係者の方に
「心理士を迎え入れることを検討してほしい」とおっしゃっています。
・支援が必要な子どもへの個別の関わりも充実するし、すべての子どもへの保育の質が高まる
・保護者が気軽に発達相談ができる
・保育士が心理士の考えや視点に触れることでさまざまな力が向上する
といった効果が期待できると。
まずは臨時職員としての雇用から、
あるいは複数の園で1人の心理士を雇用ないしは業務委託契約を締結するとか、
そうした人材シェアリングを園長会などの単位でおこなってみてはどうか、と
具体的な手立ても示してくださっています。
(あ~~~私が断られたヤツ~~~)
心理士の見つけ方やどんな心理士が望ましいかの考え方も提示してくださっています。
◎保育園に心理士がいることがあたりまえの世の中に
そんなふうになってほしいと塩谷さんはおっしゃっています。
「本書をきっかけに心理士がいる保育園が少しずつでも増え、
保育士と心理士との連携が深まっていくことで、
多職種の専門性を活かした子どもへのかかわりが普及していくことを願っています(本文より)」と。
とても賛成です!
私自身は、保育や発達、療育や心理等を学んだり経験したら
自分というひとりの人間の中に融合されていますので、
「保育士の視点」「心理士の考え」…といったように分けては考えられないのですが、
保育士や保育園のことを理解しつつ、保育士とは違った立場で発達や心・内面の育ちを大切に考えながら
保育園や子どもたちと関わりのある仕事がまたできたらいいなあと
希望を抱いております。
☆彡 いつでもお声かけくださいね!